梅毒疑いのウサギ(川崎市多摩区、オダガワ動物病院)
2019.08.19更新
 ■
■ 梅毒疑いのウサギ
梅毒疑いのウサギ
4才雄のウサギの鼻が赤くなり来院した症例です。
このウサギは2年前、梅毒を疑いクロラムフェニコールの投与でよくなりました。
鼻の綿棒検査では異常なく、梅毒の再発と考えて、再度クロラムフェニコールを投与しました。
ウサギの梅毒はこのように再発をくりかえす症例が数例います。
投稿者:

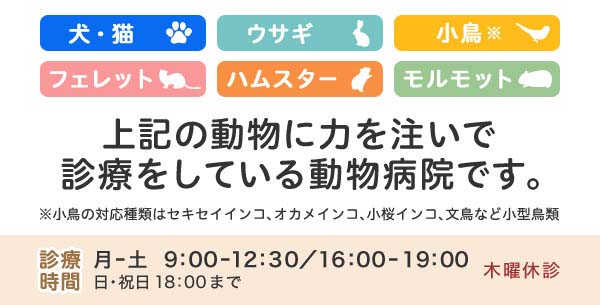
2019.08.19更新
 ■
■ 梅毒疑いのウサギ
梅毒疑いのウサギ
4才雄のウサギの鼻が赤くなり来院した症例です。
このウサギは2年前、梅毒を疑いクロラムフェニコールの投与でよくなりました。
鼻の綿棒検査では異常なく、梅毒の再発と考えて、再度クロラムフェニコールを投与しました。
ウサギの梅毒はこのように再発をくりかえす症例が数例います。
投稿者:
2019.08.09更新
 ■
■ ウサギのツメダニ症(濃厚感染例)
ウサギのツメダニ症(濃厚感染例)
8才雄のウサギの背中の皮膚が急に剥げたことで来院しました。
皮疹は鱗屑、痂皮が主体でした。
鱗屑、痂皮の部分をセロハンテープで採取し顕微鏡400倍で鏡顕しました。
ツメダニ成虫(⇧)、ツメダニ虫卵(⇧)が診られ、ツメダニによる皮膚病と診断しました。
顕微鏡を100倍の低視野にすると多くのツメダニ成虫が診られました。
しかしオーナーの稟告によればウサギは痒みを訴えていないそうです。
治療はレボリューション®を背中に滴下しました。
●17日後の来院
たいぶよくなりました。ツメダニの駆除には最低2回と投薬が必要なため、今日もレボリューション®を背中に滴下しました。1回のみ投薬だと再発するケースもあります。
投稿者:
2019.07.02更新
 ■
■ ウサギの喧嘩
ウサギの喧嘩
(写真)
学校飼育の推定4歳の雄ウサギです。
誤って2羽、同じ飼育箱に入れてしまい喧嘩をして、
眼瞼の3時方向に傷を負った症例で、(写真参照)
化膿していることが写真でわかるとおもいます。
抗生剤の全身投与と点眼をおこない経過をみました。
ウサギは学校飼育など多頭飼育の場合、
雄は縄張りを主張して、体格が同じぐらいだと
派手な喧嘩をすることが多いです。
注意して飼育されるようお願いします。
---------------------------------------------------------------------
■2週間後の来院
まだ少し喧嘩のあとはありますが、膿もなくなり良くなりました。
投稿者:
2019.06.15更新
 ■
■ ウサギの急性毛玉症
ウサギの急性毛玉症
(写真1)
6歳雌のウサギが急に具合が悪くなり来院しました。
体温は35.3度で低体温です。前肢を前に出し、犬座用姿勢をして、腹部をかばっています。
(写真2)
(写真3)
レンドゲン検査では
胃、腸に沢山のガスが診られます。
----------------------------------------------------------------------
ウサギの毛玉症は急性と慢性に分かれます。
急性毛玉症は突然、食欲不振、犬座用姿勢、低体温に陥ります。
発症の予想はつきません。鎮痛剤、胃調薬の投与で80%位は回復しますが、
死亡する場合もある怖い病気です。
上記の症状が診られた場合は早くウサギ診療可能な動物病院にいってください。
毛玉症は他に胃のうっ滞、胃拡張など獣医師により呼び名が異なります。
どれも同じ症状を指します。
投稿者:
2019.05.21更新
 ■
■ ウサギの毛芽腫
ウサギの毛芽腫
(写真1)
4歳雌のウサギの腹部に腫瘍が診られました。
この症例はオーナーとよく話して手術を行うことになりました。
血液・生化学検査、胸部レントゲンをおこない異常のないことを確認しました。
(写真2)
手術前に毛を刈るとこのような様子です。
(写真3)
イソフルレン麻酔で切除した腫瘍。
---------------------------------------------------------------------
■病理診断 毛芽腫(別名、基底膜細胞腫)
毛芽腫は表皮に存在する毛芽細胞が腫瘍性に増殖する皮膚腫瘍でウサギで多く発生します。
限局的に増殖するため、浸潤性増殖は認められないことが殆どです。
取り残しや、腫瘍が大きい場合、悪性毛芽腫も希にあり再発を繰り返します。
本症例はマージンも確保され、再発、転移の心配のない、良性の毛芽腫と診断されました。
このウサギはその後も順調に回復しています。
投稿者:
2019.02.11更新
 ■
■ ウサギの膿瘍
ウサギの膿瘍
生後2ヶ月の雄ウサギです。(ロップトイヤー種)背中にコ0.5mmの『しこり』があり、クロラムフェニコール(抗生剤)を投与して様子をみてました。
( 写真1)10日間クロラムフェニコールを投与しましたが、0.5mmの『しこり』は縮小ぜず、2cmに拡大しました。(赤矢印)
写真1)10日間クロラムフェニコールを投与しましたが、0.5mmの『しこり』は縮小ぜず、2cmに拡大しました。(赤矢印)
( 写真2)写真1の『しこり』の細胞診所見です。好中球(ウサギでは偽好酸球)が主体です。細胞診のみでは膿瘍か、腫瘍はわかりません。しかしウサギの膿瘍は抗生剤のみで治らないこともあるので、イソフルレン麻酔下で切除手術をおこないました。
写真2)写真1の『しこり』の細胞診所見です。好中球(ウサギでは偽好酸球)が主体です。細胞診のみでは膿瘍か、腫瘍はわかりません。しかしウサギの膿瘍は抗生剤のみで治らないこともあるので、イソフルレン麻酔下で切除手術をおこないました。
( 写真3)麻酔下で、毛を刈ると『しこり』はこんな様子です。皮下とは遊離しています。
写真3)麻酔下で、毛を刈ると『しこり』はこんな様子です。皮下とは遊離しています。
( 写真4.5)切除手術をした『しこり』。
写真4.5)切除手術をした『しこり』。
( 写真6)手術終了時の写真。埋没縫合して抜糸はない方法でおこなっています。
写真6)手術終了時の写真。埋没縫合して抜糸はない方法でおこなっています。
投稿者:
2019.01.02更新
 ■幼ウサギの疥癬
■幼ウサギの疥癬
購入したてのウサギの前肢に皮膚病がみられ、やたら掻くので来院しました。
拡大するとこんな様子で、痂皮、鱗屑が主な病変です。
皮膚掻爬検査をしたら疥癬(成虫)と疥癬(卵)がみつかり診断がつきました。
処置はイベルメクチン系の薬剤を使用してよくなりました。
疥癬は1回の治療でよくなることが多いですが、疥癬の卵に効果ある薬剤はないので、
3週間あけて最低2回の治療を薦めています。
1ケ月後、だいぶよくなりました。
なお
 ウサギのノミ、ダニ駆虫剤は注意が必要です。
ウサギのノミ、ダニ駆虫剤は注意が必要です。
よくかかりつけ獣医師とお話しして使用してください。
 他の動物の疥癬症
他の動物の疥癬症
■
 モルモットの疥癬
モルモットの疥癬
■
 セキセイインコの疥癬
セキセイインコの疥癬
■
 ボーダーコリーの疥癬症
ボーダーコリーの疥癬症
■
 犬疥癬はヒトに接触感染します
犬疥癬はヒトに接触感染します
■
 本院で診断のついた、ウサギの疥癬症
本院で診断のついた、ウサギの疥癬症
【関連記事】
■
 犬の診療
犬の診療
■
 猫の診療
猫の診療
■
 ウサギの診療
ウサギの診療
■
 ハムスターの診療
ハムスターの診療
■
 フェレットの診療
フェレットの診療
■
 小鳥の診療
小鳥の診療
■
 モルモットの診療
モルモットの診療
投稿者:
2019.01.02更新

■ ウサギの診療
ウサギの診療
写真・ウサギの門歯の過長
----------------------------------------------------------------------
■ 注意、薬剤
注意、薬剤
日本にはウサギの専用薬はなく、ヒト用、犬猫用でウサギに安全に使用できる薬剤を使用しています。
ウサギ、モルモット、ハムスターの薬剤特性として、①抗生剤、②ノミ、ダニ製剤は種類を間違うと死亡する薬剤もあり注意が必要です。
なお使用薬剤は動物病院により多少異なりますので、使用の際は、掛り付け獣医師によくお尋ねください。
以下、本稿では当院の見解を述べます。
■
 ウサギ・モルモット・ハムスターと抗生剤
ウサギ・モルモット・ハムスターと抗生剤
■
 ウサギ、モルモット、ハムスターに安全に使用できるノミ、マダニ製剤
ウサギ、モルモット、ハムスターに安全に使用できるノミ、マダニ製剤
----------------------------------------------------------------------
■ ウサギと内部寄生虫
ウサギと内部寄生虫
写真・ウサギのコクシジウム
■
 ウサギのコクシジウム
ウサギのコクシジウム
■
 仔ウサギの下痢
仔ウサギの下痢
■
 ウサギの蟯虫について(Passalurus ambiguus)
ウサギの蟯虫について(Passalurus ambiguus)
----------------------------------------------------------------------
 幼少期より、ときどき梅毒の症例を診ます。
幼少期より、ときどき梅毒の症例を診ます。
----------------------------------------------------------------------
ウサギは犬猫のようなワクチンで予防する疾患はありませんが特徴を考えて飼育をしないと病気の発見が手遅れになるとこがあります。
 ウサギは食欲不振時、強制給餌が重要です。
ウサギは食欲不振時、強制給餌が重要です。
■ 
 ウサギ・モルモット・ハムスターの強制給餌について
ウサギ・モルモット・ハムスターの強制給餌について
----------------------------------------------------------------------
■ 吐くことができない。(例外を除く)
吐くことができない。(例外を除く)
まず、身体の構造的に吐くということができないため、
 急性毛球症になると短時間で悪化してしまいます。具合が悪くなり体温がすぐに下がります。
急性毛球症になると短時間で悪化してしまいます。具合が悪くなり体温がすぐに下がります。
ふだんウサギは38-39度が平熱ですが、この場合35.0度ぐらいに下がります。オーナーの方もウサギが冷たくなって動かいいことを主訴に来院するケースを診ます。急性と表しているように予期なく突然おきます。気づいたらできるだけ早くウサギを診療できる動物病院に連れていってあげてください。
また、ウサギは全く食べないとわずか1日で脂肪肝になり、2~3日でいつ死亡しても不思議ではありません。例外を除き
 強制給餌の有無が生死を分けるといっても過言ではありません。
強制給餌の有無が生死を分けるといっても過言ではありません。
 強制給餌について当院ではくわしくご指導していますので、来院の際に声をかけてください。
強制給餌について当院ではくわしくご指導していますので、来院の際に声をかけてください。
----------------------------------------------------------------------
■ 皮膚関係
皮膚関係 ウサギの脱毛は独特です。
ウサギの脱毛は独特です。
■
 ウサギのアイランドスキン
ウサギのアイランドスキン
 仔ウサギの皮膚病、皮膚糸状菌症(所謂、水虫)
仔ウサギの皮膚病、皮膚糸状菌症(所謂、水虫)
■
 ウサギの皮膚糸状菌症
ウサギの皮膚糸状菌症
 ウサギの全身ジャンプー、容態が急変した症例を3例経験しているので私は禁忌と考えています。
ウサギの全身ジャンプー、容態が急変した症例を3例経験しているので私は禁忌と考えています。
■
 ウサギにシャンプーしたところ容態が急変した症例
ウサギにシャンプーしたところ容態が急変した症例
 お尻に糞をつけて生活しているウサギも診ますので注意が必要です。(写真、下)
お尻に糞をつけて生活しているウサギも診ますので注意が必要です。(写真、下)
----------------------------------------------------------------------
■ ウサギの尿は
ウサギの尿は
----------------------------------------------------------------------
■ ナイーブな動物です。
ナイーブな動物です。
ご来院いただく際には、ペットキャリーに牧草を牽いてウサギを入れてください。上記したようにウサギは身体の構造的に吐くという行為ができません。そのためペットキャリーにタオルや、ペットシーツ、新聞紙を入れると誤飲して胃腸障害をおこしますのでやめてください。
また「おとなしいから」と抱っこでご来院されると、見知らぬ場所や他の動物の気配でパニックになり取り返しのつかない結果を招くこともあります。必ずキャリーに入れて、しっかり入口を閉じてあげてください。そして診療室のなかでキャリーからだしてあでてください。
下記に当院で実際にあった事故症例を紹介します。
■
 ①家族の方が冗談でうさぎを威かしたら、小屋の中で暴れて、鼻血がでたケース。
①家族の方が冗談でうさぎを威かしたら、小屋の中で暴れて、鼻血がでたケース。
■
 ②家の電気コードを噛んで感電したウサギのケース
②家の電気コードを噛んで感電したウサギのケース
■
 ③ハーネスをつけて散歩中には外れて、壁に当たって来院したウサギ。
③ハーネスをつけて散歩中には外れて、壁に当たって来院したウサギ。
■
 ④友人に預けたら抱っこして脊髄骨折したウサギ
④友人に預けたら抱っこして脊髄骨折したウサギ
【関連記事】
■
 犬の診療
犬の診療
■
 猫の診療
猫の診療
■
 ウサギの診療
ウサギの診療
■
 ハムスターの診療
ハムスターの診療
■
 フェレットの診療
フェレットの診療
■
 小鳥の診療
小鳥の診療
■
 モルモットの診療
モルモットの診療
【break time】
 ウサギぎく(7月、月山)
ウサギぎく(7月、月山)
花びらの形がウサギの耳に似ていることからつけられたそうです。
投稿者:
2018.12.09更新

 アイランドスキン
アイランドスキン
1歳のウサギが首回りの脱毛を主訴に来院しました。
真菌、ツメダニは陰性でした。
脱毛と皮膚の境界はしっかりしていて、痒みもありませんでした。
脱毛部の中心から、しっかりした毛が生えてきており、(⇧)アイライドスキンと診断しました。
ウサギは換毛期は、区画で脱毛することが特徴で、その後脱毛の中心部から、毛が生えてくることがよくあります。
この症例はその後、無処置で発毛は診られました。
投稿者:






